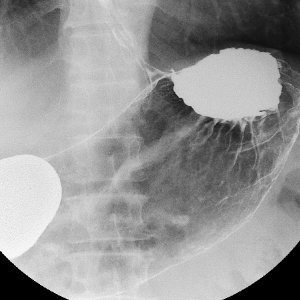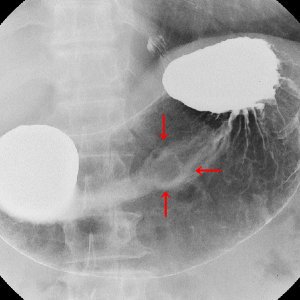みなさん、こんにちは
いかがお過ごしでしょうか![]()
前回は胃Ⅹ線検査を受けるうえで
病院を選ぶ方法の一つをご紹介しました。
近年、がん検診や人間ドックに関する
書籍を読んでいると、
胃Ⅹ線検査(バリウム検査)では
「早期の胃がんは見つからない」
「がんの見落としが多い」
と書かれているのをよく目にします。
いつも溜息が出てしまいます。![]()
技術が乏しい検者が検査を行い、
がんの存在が画像(写真)に写ってこない
そして胃がんが見つからない。
というケースは実際にあるからです。
では何故そのようなことが起こるのか![]()
胃Ⅹ線検査はバリウムと炭酸の粉を
飲んで、検査台の上でいろんな動きを
して頂く検査です。
このとき、検者は隣の部屋でモニタを見な
がらⅩ線でお腹を透視して、受診者の方に
「ゆっくり丁寧に左へ向いて下さい」などと
声をかけ、撮影ポジションを決めるための
言葉を発しています。
モニタを見ながら検査をするのは
診療放射線技師で、当然一人で行い
故にモニタ上でいかに病変に気付けるか
は、担当した技師の技量に委ねられて
いるのが現状です。
がんが存在していても、写っていない
写真ばかりを残していては
決められた枚数の撮影をしたところで
適切な診断は出来ません。![]()
下記の画像は良い例です。
通常の撮影では何も写らず
実際にはバリウムをはじく病変が!
胃がん検査は検査するものの技量が
もっとも問われる検査といっても過言では
ありません。
しかし、医師や技師といった国家資格を
もっていれば誰でも行えるということ![]()
そして、たとえ技術や知識が乏しくても
違法ではないということです。![]()
ここに大きな問題があるという訳です。
厳しく訓練や指導をして、ある程度の
レベルに成長した者だけに
一人で検査をさせる病院もあれば![]()
見よう見まねで実際の検査をさせる、
診断価値を度外視して、ただ決まった枚数
の撮影をさせるだけの病院もあります。![]()
得られる検査結果には雲泥の差が
生まれて当然な訳です。![]()
では、がんを見落とされない為には![]()
以前にも
で、書いていますが、
胃がん検診においても同じことです。![]()
前回に続き、みなさんに伝えたい
見落とされない為の病院の選び方として
ポイントの一つになるのが![]()
検査を担当した人が、読影(画像を診断)
しているかどうか、ということです。
それを報告書やレポートという形で結果を
提出しているかです。![]()
検査担当者が読影を行っていることが
優れた検査であると断言できません。
なぜなら今まで見てきた施設では
教育の一環で報告書を書かせていた
という例外もありました。
ですから
反対に読影をさせていない施設は
考えものです。![]()
検査を受けるとき、それとなく
誰が読影をするのか聞いてみて下さい。![]()