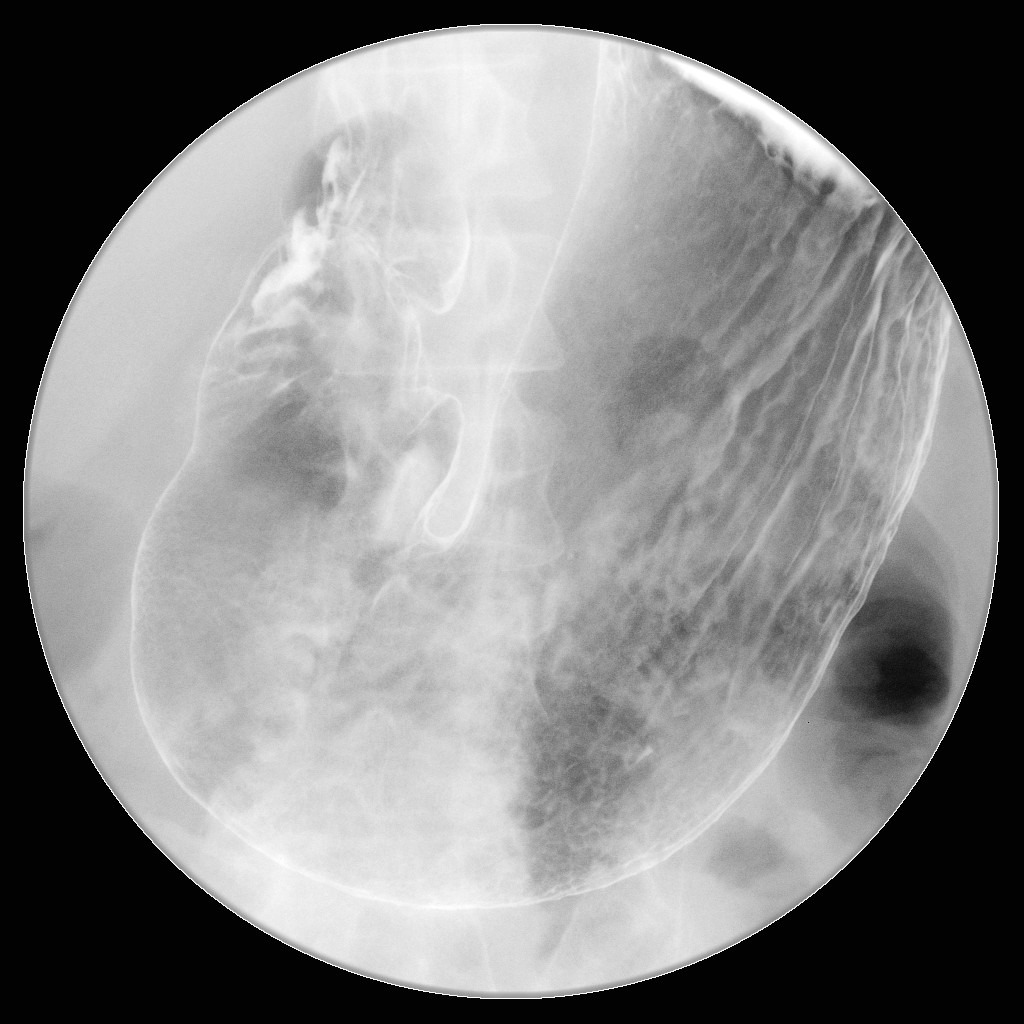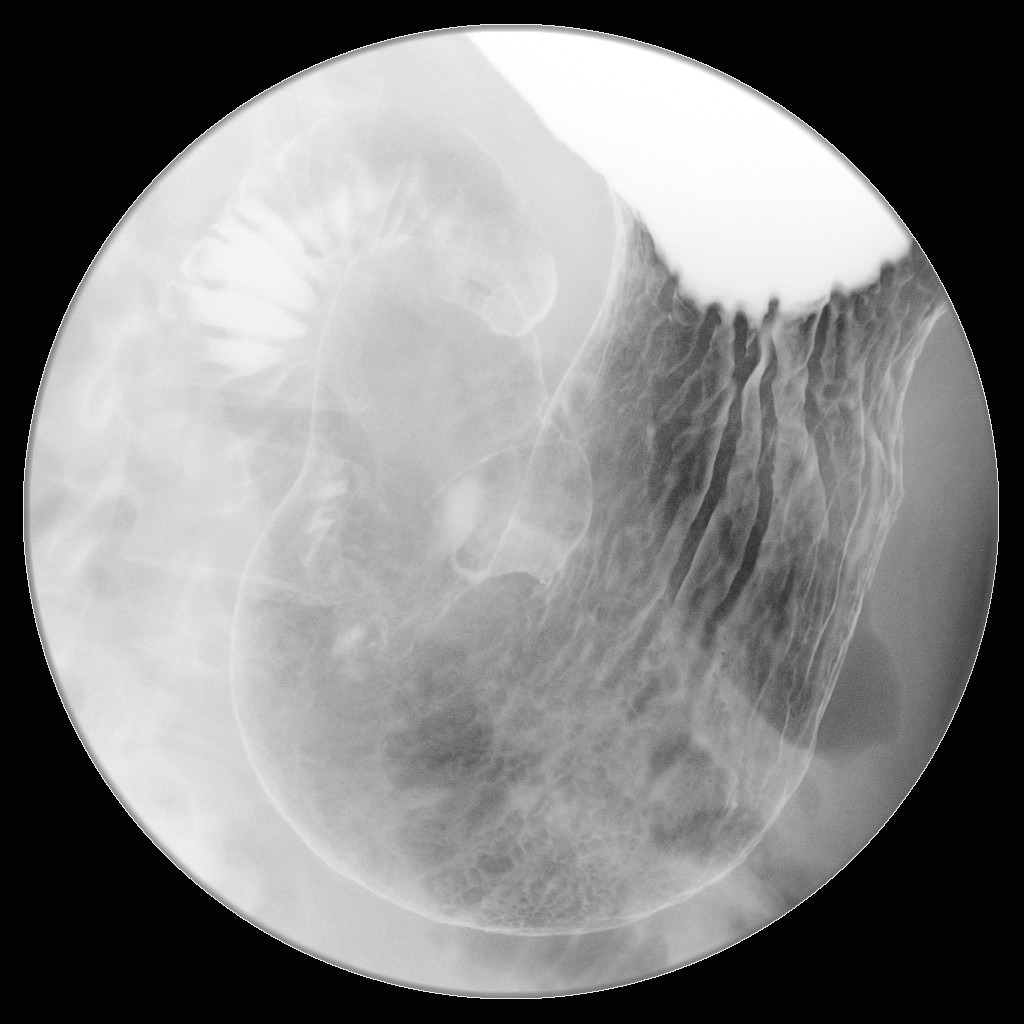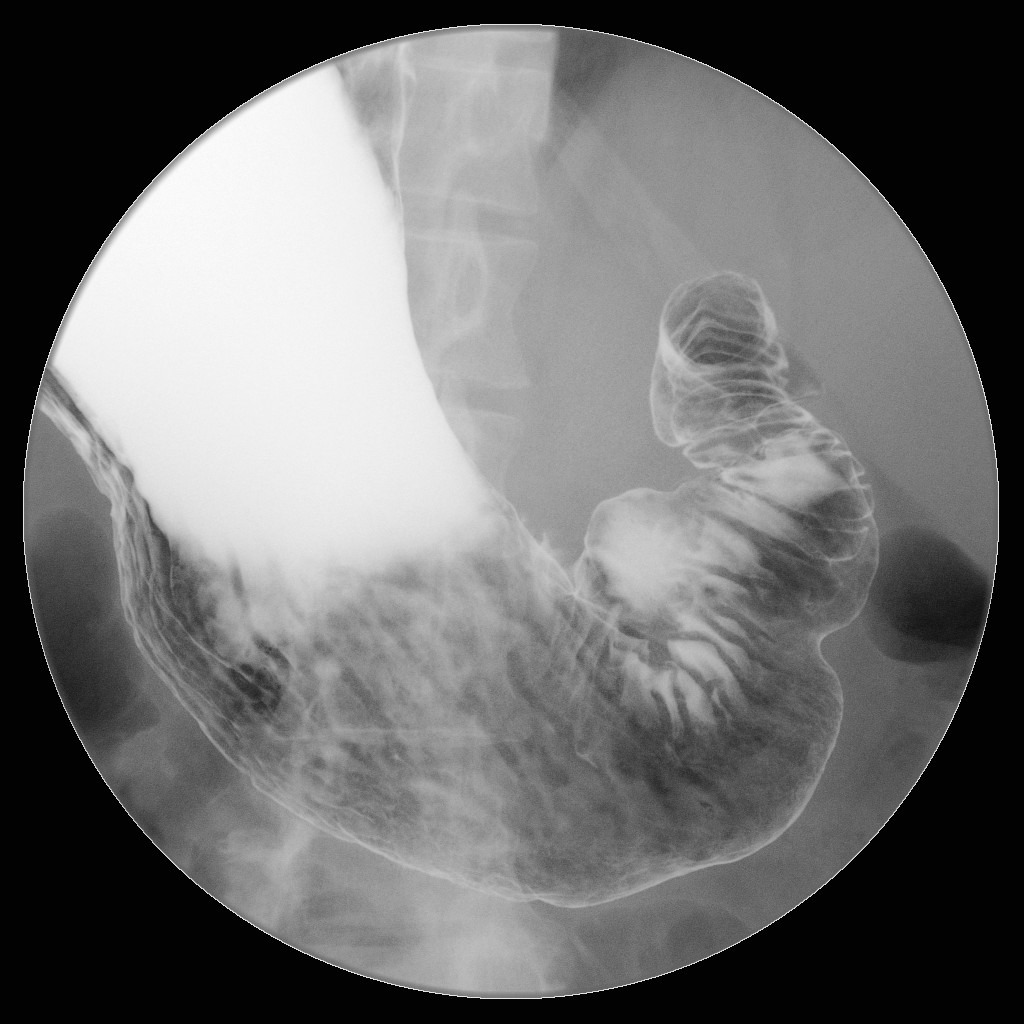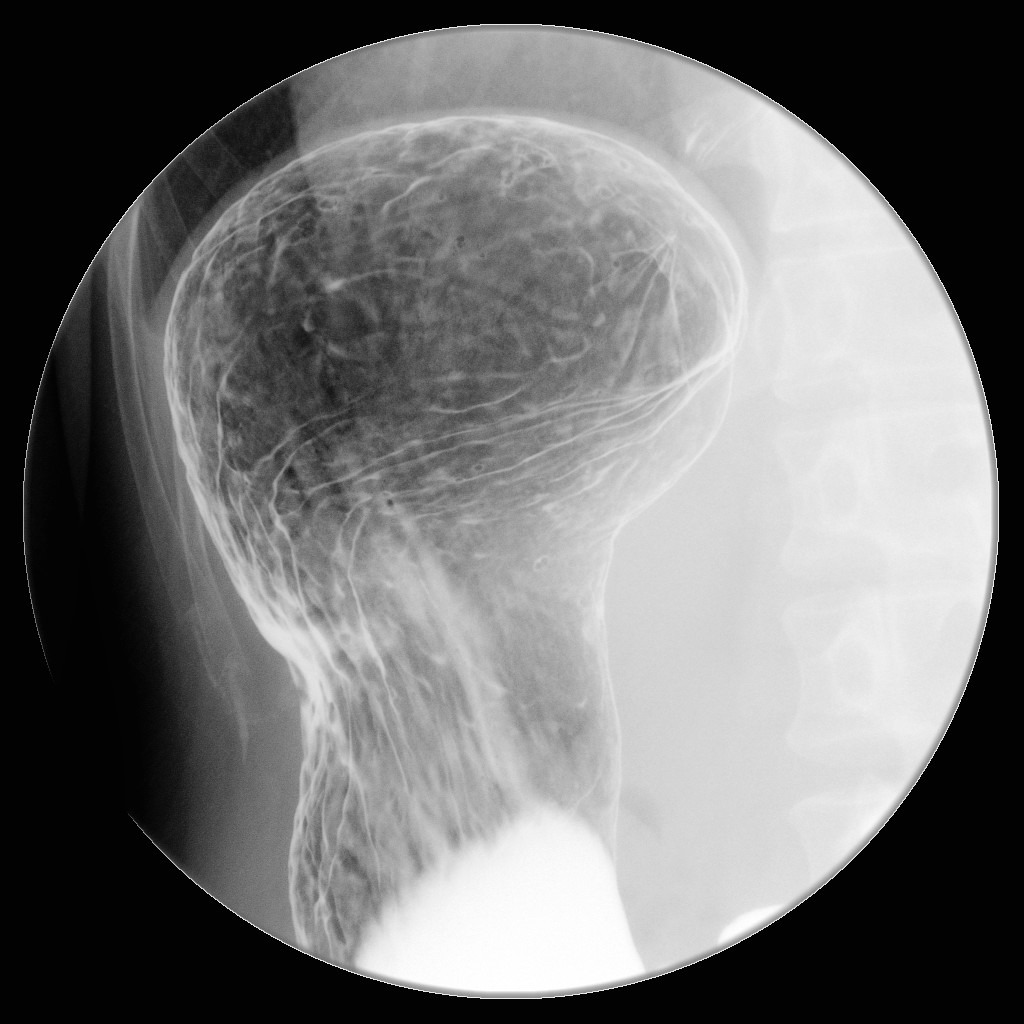みなさん、こんにちは
いかがお過ごしでしょうか![]()
前回は
ということで、見落としが起きる理由と、
見落とされないようにする工夫の
ポイントを一つ書いてみました。![]()
胃がんは日本人に最も多いがんです。
そのため胃がん検診を普及させるあまり
検診施設によっては、がんを見逃すなど
質の悪い検査を行っているところも
存在しています。![]()
受診者の方々にとって
胃がん検診は、早い段階で胃がんを見つけ
今の暮らしを保つことにあると思います。
けっして、検診施設へ利益をもたらす為
ではないはずです。![]()
ですから
受ける側は、もっと胃がん検診について
知らなくてはいけない、と思う次第です。
例えば
一言に胃Ⅹ線検査といっても、人間ドックや
自治体の胃がん検診では、検査の内容が
異なるのはご存知でしたでしょうか![]()
バリウム、炭酸、それに使う装置も同じ
なのですが、撮影枚数と一人の検査に
費やす時間が異なるのです。![]()
自治体の胃がん検診は、撮影枚数8枚と
決まっていますが、人間ドックでは
施設ごとに撮影方法がバラバラです。![]()
ただ胃がん検診の8枚よりは多いです。
何故なら、8枚というのは最低限の検査で
それより多い方が検査精度が良いからです。
しかし、私は胃がん検診で結構「がん」を
見つけています。![]()
胃がん検診は最低限の8枚しか、撮影をして
いませんが、その中でも質の悪い検査を
見抜くポイントとして、検査時間に着目する
と良いです。![]()
一般の40~50代の受診者を検査した場合、
1人の検査時間に3分程かかります。
高齢者ですともう少し要しますね![]()
これが2分程度で終わっているようでは
質の良い検査は不可能です。![]()
特に検診車によるバリウム検査では
診断価値を度外視して、短時間に多くの
数をこなす傾向が、未だ多いようです。![]()
ただし、「運」がよければ「早期のがん」が
見つかることはあります。![]()
もし、時間の短さに気づいたら
「1人2分くらいでは検査の質が悪いと
聞いたんですけど本当に大丈夫ですか?」
と尋ねて頂きたいです。
それが胃がん検診の質を高めることに
繋がると考えています。![]()